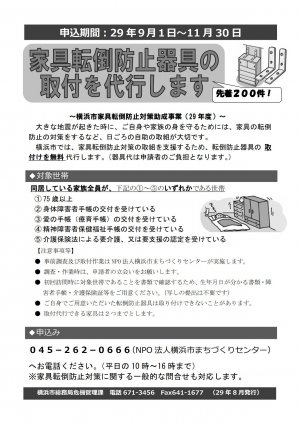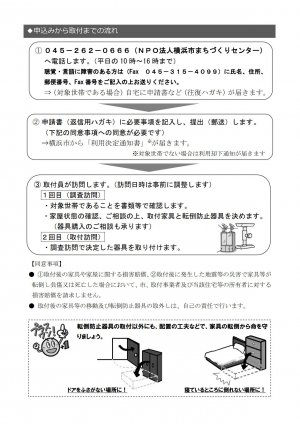防災出前講座 in 沢渡三ッ沢地域ケアプラザ
活動報告
「防災出前講座(家具転倒防止対策編)
in 沢渡三ッ沢地域ケアプラザ」
開催日時:平成29年9月19日(火)10:00~11:30
会場 :沢渡三ッ沢地域ケアプラザ
参加者 :9名(お子様1名含)+ケアプラザ職員3名
*******************************
9月は防災月間ですね!
今回は、沢渡三ッ沢地域ケアプラザからの依頼を受け、
地域の方の防災意識を高め、
家具転倒防止対策を普及啓発する出前講座を行いました。
講師の王子氏の流暢な語りに、参加者は初めから話にグイグイ引き込まれていきました。
「よく、地震が来たらそのまま死んじゃってもいいわって言う方がいますが、
見つけた近所の人や消防職員は助けなくてはいけないんですよ!
他の人に迷惑をかけないように自分の身は自分で守る、これを徹底してください。」
地震が来たら、「まずは命を守る!」
その命を守るために事前に出来て、しかも簡単なことは、「家具の固定」です。
いくら建物の耐震改修がされていても、
家具が固定されていなければ圧死や大怪我の可能性が非常に高くなります。
参加者の皆さんは、家具を固定していない状態で地震が来た映像を見て
恐ろしさを理解されたと思います。
********************************
後半は、実演を見て理解し、参加して習得します。
器具の取付位置が適性でないと、いざという時に簡単に外れてしまいます。
講師の刈山氏がどなたかやってみませんか?と声をかけると、
参加者全員が立ち上がり、代わるがわる体験しました。
特に、インパクトドライバーを使ってネジを締めつける作業は人気でした。
簡単そうに見えますが、意外と難しく感じた方が多かったようで、
参加者からは、やっぱりプロに頼んだほうがいいな~という声が上がりました。
*******************************
NPO法人横浜市まちづくりセンターでは、
家具転倒防止器具取付工事業者紹介を行っております。
現在(9月1日~11月30日まで)は、
横浜市から委託を受け、
家具転倒防止対策助成事業も行っております。
この事業は利用できる条件がありますが、プロの建築士による
適正な位置に家具を固定する費用(取付代や出張費)が無料になります。
(器具代のみ別途必要)
***********************************
また、今回のような防災出前講座も行ってっておりますので、
電話またはメールでお問い合わせの上、どうぞご利用ください!